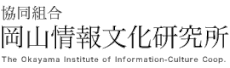真庭市/蒜山の郷原漆器
【vol.06】ひるぜんのごうばらしっき
蒜山で継承される古来からの技法、全国に誇るべき岡山の伝統漆器。

▲全国的にも珍しい製法で作られる、蒜山の郷原漆器。輪切りしたヤマグリの生木から年輪を中心にして、ろくろで器の形に削り出すため、漆器の側面に美しいヤマグリの木目が現れる。使うほど表情が深くなる

▲「蒜山にしかない文化を絶やしてはいけない。自分がいることで、郷原漆器をどうにか未来へつなげられたら」と信念を語る『郷原漆器の館』館長、ディロング・デービッドさん
全国的にも珍しい、古の漆器が岡山に。
真庭市蒜山地区の特産品で、岡山県の重要無形民俗文化財に指定されている「郷原漆器」。雄大な蒜山三座の南西にある集落・郷原で作られたことから、その名がついた。日本の漆器といえば、石川県の輪島塗や京都の京漆器が有名だが、郷原もかつて中国地方有数の生産地として名を馳せた。そして、ほかの産地では見られなくなった古の技法が今も息づいている。
最大の特徴は、ヤマグリの生木を用いる点にある。通常の漆器は、約一年程度乾燥させた木で作るが、郷原は水分をたっぷり含んだ生木を輪切りにして、まずは年輪の芯を中心に一気にろくろで器の形に挽き、その後に乾燥させる。これにより乾燥期間は半年に短縮され、生産量も上がるうえ、器は乾きながら芯に向かって均等に縮むため、割れやゆがみが少ない。また多くの漆器は木目が隠れるほど漆を重ねるが、郷原漆器は数回程度で薄く塗るため木目が際立って美しい。戦前は漆を重ね塗りして蒔絵や沈金を施した豪華な器も作られたが、主力は暮らしの器で、質がよく安価なため、広く重宝された。

▲素材は、水分を含んだ乾燥前のヤマグリの生木

▲年輪を中心にろくろで器の形に木を挽いていく

器に形成した後で半年乾燥させる、珍しい工程
蒜山でなければ生まれなかった背景を知る。
郷原漆器を研究する『真庭市蒜山郷土博物館』の前原茂雄館長は、「郷原漆器は、蒜山でなければ生まれなかった」という。「郷原漆器の歴史は、これまで約600年とされていましたが、最新の研究から江戸時代前期の1600年代、約400年前からと考えられています。山深い蒜山の小さな集落に伝わるその製法は、今では大変貴重なものとなりました。その誕生の背景には、4つの条件が挙げられます。
ひとつめは山間で森林資源が豊富だったこと。蒜山の土壌は噴火した大山の火山灰が堆積していて、ヤマグリの生育と相性がよく器の材料に恵まれました。二つめは塗料の漆も多く自生していたこと。三つめは寒冷多湿気な気候だったこと。湿気が高いほどよく乾燥して定着する漆の性質に適した環境でした。四つめは出荷ルートがあったこと。霊峰・大山に詣でる大山道や山陰への往還道が整備され、松江や米子、出雲への販路がありました。豪雪地帯で多湿な気候は人の暮らしに不利ですが、蒜山の人々は厳しい自然に知恵と工夫をもって向き合い、地元産業を発展させたのです」。

▲「郷原漆器ほど個性的な漆器はほかにありません。それが岡山県にあることを知ってほしい」と、『真庭市蒜山郷土博物館』前原館長

▲『真庭市蒜山郷土博物館』では戦前の郷原漆器と道具、その歴史などを知ることができる

▲生漆を精製する道具クロメバチとカイ
盛衰の歴史を越えて継承される伝統文化。
生活に密着した郷原漆器の生産は、明治時代末期から大正時代末期に最盛期を迎える。山の中で木を伐採し、器の形に挽いて持ってくる木地師や、その器に漆を塗る塗師、下塗師や蒔絵師、また沈金師など多くの職人たちと、買い付けにくる商人、運送人。郷原集落は、関係者で大いに賑わったという。しかし、そんな郷原漆器に危機が訪れる。大量生産の結果、材料不足に陥り、さらに一九三〇年の昭和恐慌で経済が悪化。第二次世界大戦で漆が国の統制品となり、職人が徴兵されるなどで後継者がいなくなり、昭和二〇年に生産が途絶えてしまう。戦後もプラスチック製品の普及で生活様式が激変し、復興しないままだった。
そんななか一九八五年、岡山県郷土文化財団が、地元有志と旧川上村とともに復興に向けて調査・収集を開始する。そして一九八九年に「郷原漆器生産振興会」が発足、『郷原漆器の館』を拠点に再び郷原漆器の生産が始まった。小さな集落に残る伝統文化を絶やしたくないと思う多くの人々が尽力し、その情熱は二〇二四年四月からアメリカ出身のディロング・デービッドさんに引き継がれている。

▲優美な蒜山三座がシンボルの蒜山高原。郷原漆器はこの大自然の暮らしの知恵と工夫から生まれた
▲郷原漆器を伝承する拠点、『郷原漆器の館』。1階が木地作り、2階が漆を塗るための工房になっている


▲ヤマグリの生木で形成した器は乾燥により6~8mm縮小する。個々に違う微妙な違いが味わいになる
盛衰の歴史を越えて継承される伝統文化。
生活に密着した郷原漆器の生産は、明治時代末期から大正時代末期に最盛期を迎える。山の中で木を伐採し、器の形に挽いて持ってくる木地師や、その器に漆を塗る塗師、下塗師や蒔絵師、また沈金師など多くの職人たちと、買い付けにくる商人、運送人。郷原集落は、関係者で大いに賑わったという。しかし、そんな郷原漆器に危機が訪れる。大量生産の結果、材料不足に陥り、さらに1930年の昭和恐慌で経済が悪化。第二次世界大戦で漆が国の統制品となり、職人が徴兵されるなどで後継者がいなくなり、昭和20年に生産が途絶えてしまう。戦後もプラスチック製品の普及で生活様式が激変し、復興しないままだった。
そんななか1985年、岡山県郷土文化財団が、地元有志と旧川上村とともに復興に向けて調査・収集を開始する。そして1989年に「郷原漆器生産振興会」が発足、『郷原漆器の館』を拠点に再び郷原漆器の生産が始まった。小さな集落に残る伝統文化を絶やしたくないと思う多くの人々が尽力し、その情熱は2024年4月からアメリカ出身のディロング・デービッドさんに引き継がれている。

▲『郷原漆器の館』2階の工房で漆を塗り、すぐにふき取る「拭き漆」をするデービッドさん
ビジョンと志を持って郷原漆器を未来へ。
「私は、日本のどの漆器より郷原漆器に特別な価値と魅力を感じています」とデービッドさん。規格通りの工業製品と違い、ひとつずつ手作りで表情がある器だからこそ愛着が湧くという。「郷原漆器は面白い漆器です。ヤマグリは癖の強い材質なので、素直な木地もあれば、融通のきかない、やんちゃな木地もあって、まるで人間みたいです(笑)。それぞれの個性を生かして仕上げていますが、本当の完成はみなさんが実際に使って、洗ったり拭いたりするうち艶や感触が変化してベストな状態になったときなので、ぜひ器を育てるような気持ちで使ってほしいと思います。そうして好きになってもらい、郷原漆器のファンが地元真庭市から、県北・県南へと広がることを願っています」。

▲右は原液の生漆と、それを吸った「木固め」という下塗りの状態。約1週間おいて乾燥したら表面を磨き、また漆を塗る作業を数回。左は塗料用の精製した漆と、上塗りして「拭き漆」をした状態
デービッドさんは、多くの人に届けたいと思いながらも、過去の苦い歴史を知り、需要と供給のバランスを崩さないよう年間生産数は約一〇〇〇個に設定。そして、自らもヤマグリと漆を植栽し、完全に育つまで一五年は伐採しないという。「郷原漆器は、蒜山の自然の恵みそのものです。生産が始まった江戸時代の原点に返って自然に感謝しながら木の器を使い、劣化したら自然へ還す。循環型の生活のなかで郷原漆器が未来へ継承されることが理想です」。
木の器を使えば、自然と社会の関わりに気持ちを寄せる時間が増えるとデービッドさんは志を高くする。古来の技法を伝える郷原漆器は歴史だけでなく未来を大切に考えるきっかけもくれる。岡山に郷原漆器があることを誇りにしたい。
●『郷原漆器絵付け体験』はこちら

※漆はウルシオールという成分を含みアレルギー反応が出る場合があるので、各自でよく注意をすること
2025年9月14日(日)、10月12日(日)10:00~(約2時間)
『郷原漆器絵付け体験』をこちらで体験
※2日前までに要予約。申込みの詳細はHPを要確認
絵付けを通して蒜山に伝わる伝統の手仕事、郷原漆器にふれる体験。ディロング・デー
ビッドさんが作った、郷原漆器のおちょこや皿、小鉢や大小の椀に、オリジナルの絵付けをして自分だけの器に仕上げていく。漆は、色漆が用意されていて、カラフルな絵を描くことも可能。完成したら漆が乾燥するまで約2週間、飲食用に完全に乾くまで約3か月かかる。箱に固定して持ちかえるか、後日取りに行くか、発送を依頼。
会場:郷原漆器の館
住所:真庭市蒜山上福田425
料金:体験料1800円プラス漆器代2500~8000円 ※器によって異なる
申し込み・問合せ:観光局
電話:0867-45-7111
URL https://www.maniwa.or.jp/web/index.cgi?c=tour-2&pk=155
※『オセラ2025年8月25日号』にて掲載。
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください。